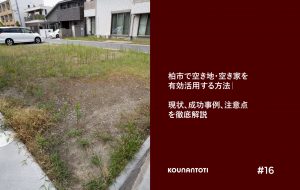相続した空地で悩んでいませんか?我孫子市の空地問題と解決方法を紹介

目次
- はじめに|相続で「空地を持つことになった方」へ
- 第1章 相続で空地が発生する典型的なケース
- 第2章 相続した空地を放置するリスク
- 第3章 相続空地の解決策
- 3-1. 売却する場合の流れとポイント
- 3-2. 活用する場合の選択肢
- 3-3. 共有名義の場合の注意点 - 第4章 我孫子市の空地と相続に関する行政の取り組み
- 第5章 まとめと次のステップ
はじめに|相続で「空地を持つことになった方」へ
「親から土地を相続したけれど、どう使えばいいのかわからない」
「古家を解体したら空地になってしまい、管理に困っている」
「兄弟と共有名義になっていて、処分の話がまとまらない」
こうしたお悩みを抱える方は、我孫子市内でも少なくありません。特に『相続』は突然やってくるケースが多いため、どうしていくのか決まっていない場合が大半です。「とりあえずそのままにしている」という状況になりがちなのです。しかし、空地を放置していると 固定資産税の負担・雑草や不法投棄の管理リスク・将来的な売却価値の低下 など、見えないデメリットがいつのまにか増えてしまうのです。
この記事では、相続によって発生する空地問題に焦点を当て、相続によって起こるリスクや問題、その解決策や我孫子市の取り組みについてをまとめて解説いたします。
- 相続で空地が生じる典型的なケース
- 空地を放置するリスク
- 売却や活用といった具体的な解決策
- 我孫子市の行政による取り組み
相続空地で悩んでいる方、いずれ相続されるかもしれない、という方にとって「自分にとってぴったりの選択肢」を見つけられるよう、私たち『晃南土地』 のスッタフが解説いたします。
第1章 相続で空地が発生する典型的なケース

相続をきっかけに「空地を持つことになった」という方は、想像以上に多くいらっしゃいます。特に我孫子市のように戸建てが多く、長年住み継がれてきた住宅地では、「親が亡くなったあとに住む人がいなくなった」「古家を取り壊して更地にした」というケースが典型です。この章では、相続で空地が生じる代表的なパターンを整理しながら、それぞれの背景や課題を見ていきましょう。
1-1. 親から住宅を相続 → 解体して更地に
もっとも多いのが、親が住んでいた戸建て住宅を相続したものの、自分自身は別の場所に住んでいるため利用できず、古くなった建物を解体して更地にしたケースです。
解体の背景には以下のような事情があります。
- 建物が老朽化して安全面で不安がある
- 耐震性や設備面で現代の基準に合わない
- 賃貸として活用するには修繕費が高額になる
我孫子市の場合、昭和40〜50年代に建てられた木造住宅が多く残っており、築40年以上を経過している物件も珍しくありません。こうした物件は解体されるケースが増えており、結果として「空地」が生まれるのです。
1-2. 農地や使っていない土地を相続
もう一つの典型が、親や祖父母から農地や郊外の土地を相続するパターンです。
かつては農業を営んでいた家庭でも、次の世代が農業を継がずに土地だけが残ることがあります。特に我孫子市では、手賀沼周辺や郊外エリアに農地や宅地予定地が多く、住宅地から少し離れた場所にまとまった土地を相続するケースも目立ちます。
ただし農地は「農地法」の制限がかかるため、自由に売却や転用ができないのが難点です。そのため「使えないまま放置」され、雑草や不法投棄の温床になってしまうことも。行政が市民農園として活用している一方で、個人所有の農地が空地化してしまう例も少なくありません。
1-3. 相続した土地が共有名義になったケース
兄弟姉妹で土地を共同相続し、共有名義となるケースも多いです。
例えば「実家を兄弟で相続したが、誰も住まないので更地にした」といった場合、その土地は複数人の共有名義となります。このとき問題となるのは、売却や活用の意思決定がスムーズにいかないことです。
- 売却を希望する兄弟と、保有を希望する兄弟が対立
- 活用に必要な初期投資の分担で揉める
- 将来的に相続人がさらに増え、権利関係が複雑化
こうした共有状態の空地は「塩漬け」となりやすく、誰も使わないのに税金だけが発生するという悪循環を生みがちです。我孫子市のように住宅需要がある地域であっても、権利関係が複雑な土地は市場に出しにくいため、空地のまま残ってしまいます。
1-4. 相続で生じる「想定外の空地」
近年増えているのが、「想定外の空地」を相続するパターンです。
- 亡くなった親が投資用に購入していた土地
- 相続するまで存在を知らなかった土地
- 遠方にあり、現地確認すらできていない土地
我孫子市でも、都内に住む子世代が「地元に戻る予定はないが、土地だけ相続した」という事例が多く見られます。この場合、相続人にとっては「価値があるのかどうかもわからない土地」を抱えることになり、どう処分・活用するかで悩むことになります。
まとめ:空地相続は「誰にでも起こり得る」問題
相続で空地が発生する背景はさまざまですが、共通するのは「突然の相続で、具体的な使い道を決めないまま土地を持つことになった」という点です。
- 古家を解体した結果の更地
- 農地や郊外の使っていない土地
- 兄弟姉妹での共有土地
- 想定外の土地を引き継いだケース
どのパターンでも、放置しておけば 税金・管理リスク・資産価値低下 につながるのは避けられません。つまり空地の相続は「相続税や名義変更だけの問題」ではなく、その後の 活用・売却・維持管理まで考える必要がある課題 なのです。
第2章 相続した空地を放置するリスク

相続によって手に入れた土地を「とりあえず何もせず持ち続ける」――これは決して珍しいことではありません。実際に我孫子市でも、「名義変更はしたけれど、特に活用せずそのまま」という空地が数多く存在しています。
しかし、空地を放置すると目に見える以上に大きなリスクが積み重なっていきます。ここでは、我孫子市に住む方々や相続で土地を得た方にとって、現実的に起こり得るリスクを整理してみましょう。
2-1. 税金・維持管理費の負担
空地は「使っていなくても税金がかかる」という厳しい現実があります。
- 固定資産税:土地の評価額に基づいて毎年課税。住宅が建っていれば軽減措置(住宅用地特例)が適用されますが、更地にするとその特例が外れるため、税額が大幅に上がることがあります。
- 都市計画税:我孫子市は市街化区域に含まれる土地も多く、都市計画税も加算されるケースがあります。
加えて、草刈りや樹木の伐採などの維持管理も必要です。特に夏場は雑草の伸びが早く、放置すると近隣から苦情が入ることもあります。専門業者に依頼すれば1回数万円の費用がかかり、年に数回繰り返すと大きな出費になってしまいます。
2-2. 不法投棄や治安面でのトラブル
利用されていない土地は「人目が少ない場所」となり、不法投棄や不審者の侵入といったリスクが高まります。
- 家電やタイヤなどの粗大ごみを勝手に捨てられる
- 空き缶やたばこの吸い殻などで近隣環境が悪化する
- 青少年のたまり場になり、治安が悪化する
こうした状況が続けば、地域のイメージを損ない、いざ売却や活用を考えたときに「環境が悪い場所」として価格が下がってしまうこともあります。我孫子市は子育て世帯が多い地域ですから、「安全性の低い土地」という印象は致命的になりかねません。
2-3. 資産価値の低下
土地の価値は「立地」「需要」「環境」で決まります。空地を放置することは、これらすべてにマイナスの影響を与える可能性があります。
- 雑草や樹木で荒れ果てた印象 → 見た目で価値が下がる
- 周辺が住宅地として発展しても、活用されないまま取り残される → 需要に合わず売りにくい
- 近隣から「迷惑な土地」と見られる → 評判が落ち、取引価格に影響
特に我孫子市は駅周辺の再開発や新築需要が動いているエリアも多いため、「タイミングを逃して価値が落ちる」ケースが起こり得ます。
2-4. 行政からの指導対象になる可能性
我孫子市では平成30年に「空家等対策計画」を策定し、令和5年にも改定を行っています。これにより、危険な建物や管理不十分な空地に対しては、市から指導や勧告が入る可能性があります。
- 草木が道路にはみ出している
- ゴミが不法投棄されたまま放置されている
- 近隣からの苦情が寄せられている
こうした場合、市から改善を求められ、最悪の場合は行政代執行(費用は所有者負担)となることもあります。つまり「ただ置いておくだけ」のつもりでも、実際には行政のチェック対象になってしまうのです。
2-5. 家族や相続人への負担
「自分の代ではそのままでいい」と思っていても、次の世代に負担を先送りすることになりかねません。
- 固定資産税や管理の手間を子世代に引き継ぐことになる
- 共有名義のまま放置すると、さらに相続人が増え、権利関係が複雑化
- いざ売却しようとしたときに「誰が権利を持っているのか分からない」という事態に
こうなると処分に何年もかかり、最終的に「負動産(持っているだけで負担になる資産)」になってしまう危険もあります。
まとめ:放置は「一番高くつく選択肢」
空地を持ち続けること自体は悪いことではありません。しかし「何もせずに放置する」というのは、最もコストがかかり、最も価値を損なう選択肢です。
- 税金と管理費が毎年発生する
- 不法投棄や治安悪化のリスク
- 資産価値が下がり、売却しづらくなる
- 行政からの指導対象になる可能性
- 子世代に負担を先送りする
つまり「とりあえず放置」というのは、実は一番リスクの高い選択なのです。
第3章 空地を『売却』する流れ

「相続した空地を手放そう」と決めたとき、多くの方が気になるのは 「どういう手順で進めればいいのか」 という点です。売却は大きなお金が動くため、不安や疑問がつきもの。ここでは、実際の流れを整理しつつ、我孫子市で売却を検討される方にとって押さえておきたいポイントを解説します。
3-1. まずは土地の現状を把握する
売却を検討する際、最初に必要なのは「土地の現状を正しく把握すること」です。
- 登記簿での名義確認:相続登記が済んでいない場合は、まず名義変更が必須です。2024年4月から相続登記は義務化されており、手続きを怠ると過料が科される可能性もあります。
- 境界の確認:隣地との境界があいまいなままでは売却が進みません。測量をして「境界確定書」を整えておくと、後のトラブル防止につながります。
- 用途地域や接道状況の確認:市街化区域か、市街化調整区域かによって売れる相手が変わります。接道義務を満たしていないと建築ができず、価格が下がることもあります。
まずは「売れる土地なのか」「売るために整えるべき点があるのか」を明らかにしておくことが重要です。
3-2. 不動産会社へ査定を依頼する
現状を整理したら、次は不動産会社に査定を依頼します。
- 机上査定:地図や公示地価などのデータをもとにおおまかな金額を算出。短期間で出ますが、正確性はやや低めです。
- 訪問査定:現地を確認し、周辺環境や接道状況、土地の形状などを踏まえて具体的に金額を提示。売却の検討段階ではこちらがおすすめです。
我孫子市内でも駅近・住宅地・郊外などで価格差が大きく、同じ面積でも数百万円単位で差が出ることがあります。複数社に依頼し、相場感を掴むことが大切です。
3-3. 売却方法を選ぶ
査定額を踏まえて「どう売るか」を選択します。
- 仲介:一般的な方法。不動産会社に買い手を探してもらい、相場に近い価格で売却できます。期間は数か月~半年が目安。
- 買取:不動産会社に直接買い取ってもらう方法。価格は相場より下がりますが、短期間で現金化でき、手間も少ないのが利点です。
- 分割販売:広い土地を小さく区切って売る方法。時間とコストはかかりますが、全体の売却益を高められることもあります。
我孫子市では、常磐線沿線の駅徒歩圏内は仲介で買い手が見つかりやすく、郊外の農地に近い土地などは「買取」の方がスムーズに進む傾向があります。
3-4. 売却活動と契約
売却方法を決めたら、不動産会社が広告やネット掲載などで買い手を探します。
- 広告の工夫:写真や紹介文を整えることで印象が大きく変わります。最近ではドローン撮影で土地全体を見せるケースも増えています。
- 内覧・現地案内:買い手が現地を確認し、購入意思を固めていきます。
その後、条件がまとまれば売買契約を締結します。手付金の受領、重要事項説明の確認など、手続きは法律に基づいて進められるため、専門家のチェックを受けながら安心して進めることができます。
3-5. 決済と引き渡し
契約後、買主がローンを組む場合は金融機関の審査などを経て、決済・引き渡しが行われます。
- 売却代金の入金
- 所有権移転登記
- 鍵や土地の引き渡し
ここまで終わって初めて「売却が完了した」といえます。
3-6. 売却にかかる税金や費用
売却には費用も発生します。
- 仲介手数料(仲介の場合):売却価格の3%+6万円+消費税が上限
- 登記費用:相続登記や抵当権抹消などが必要な場合
- 測量費用:境界確定に必要
- 譲渡所得税:売却益が出た場合、所得税・住民税が課税
ただし相続空地には「空き家特例」などの税制優遇が適用できる場合があり、条件を満たせば数千万円単位で非課税になるケースもあります。売却を検討する際は、必ず税理士など専門家に相談してみましょう。
まとめ:売却は「流れを知ること」で安心できる
相続した空地を売却する流れは、以下のようになります。
- 現状を把握する
- 査定を依頼する
- 売却方法を選ぶ
- 売却活動・契約
- 決済・引き渡し
「何から始めればいいのか分からない」と悩みがちですが、この流れを頭に入れておけば安心して進められるのではないでしょうか。特に我孫子市は駅近や住宅地の需要が安定しているため、タイミングを逃さなければ売却がスムーズに進む地域。「動き出すなら今」という意識で、まずは査定からスタートしてみてはいかがでしょうか。
第4章 空地を売らずに『活用』する流れ

「売却してしまうのは惜しい」「将来的に子や孫に残したい」——そんな思いから、空地を活用して収益や地域とのつながりを生み出す選択をされる方も増えています。我孫子市は都心からのアクセスが良く、自然も豊かなため、立地によってさまざまな活用方法が考えられます。ここでは代表的な活用法と、進め方の流れをご紹介します。
4-1. 駐車場経営
最も始めやすい活用法のひとつが駐車場経営です。
- 土地を整地(砂利敷きや舗装)
- 月極として貸すか、コインパーキング機器を設置するかを選択
- 管理会社や運営会社に委託してスタート
我孫子市ならではの特徴
- 車の所有率が高く(千葉県の自動車保有台数は全国でも上位)、駅から徒歩10分以上のエリアでは「2台目・3台目用」の駐車場ニーズがあります。
- 駅周辺は既に競合が多いため、少し離れた住宅街や新興住宅地での需要を狙うのが現実的です。
注意点
- アスファルト舗装は初期投資が高額ですが、利用者からの印象は良く、稼働率が安定しやすい。
- 砂利敷きなら低コストで始められますが、雨の日に泥はねがあるなど利用者から敬遠されることもあります。
4-2. アパート・賃貸住宅の建築
土地が広い場合は、アパートや賃貸住宅を建てて運用する方法もあります。
- 不動産会社や建築会社にプランを依頼
- 融資の検討(建築費用は数千万円単位)
- 入居者募集・管理体制を整える
我孫子市ならではの特徴
- 中央学院大学や川村学園女子大学があり、学生向け賃貸需要が一定数ある。
- NECプラットフォームズや研究所などの企業も立地し、単身赴任者や転勤族のニーズも見込めます。
注意点
- 建築コストと利回りのバランスを見誤ると赤字になるリスクあり。
- 空室リスクを常に意識し、管理会社と連携した戦略的運用が不可欠です。
4-3. 市民農園や貸地としての活用
郊外や住宅地の一角に空地をお持ちなら「市民農園」として貸し出す方法もあります。
- 土地を区画に分ける(10〜20㎡程度が一般的)
- 契約条件を設定し、地域住民へ募集
- 水道や簡易トイレの整備を行うと利用者の満足度が高まる
我孫子市ならではの特徴
- シニア層が多く居住しており、退職後に家庭菜園を始めたいニーズが高い。
- 手賀沼周辺では農業体験イベントや直売所が盛んで、地域ぐるみの利用促進につなげやすい。
注意点
- 収益性は低め。地域貢献や維持管理の一環と考えると現実的。
- 雑草や農薬の使用など、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあるため、ルール作りが重要。
4-4. 資材置き場・太陽光発電用地
建築会社や運送業者向けに資材置き場として貸す、あるいは太陽光発電用地として活用するケースもあります。
我孫子市ならではの特徴
- 常磐線沿線で建築需要が継続しているため、資材置き場需要は一定数ある。
- 日当たりの良い郊外地であれば太陽光発電の設置も現実的。ただし初期費用や売電価格の下落リスクを考慮する必要があります。
4-5. 空地活用の注意点
活用には魅力がある一方で、落とし穴もあります。
- 初期投資の大きさ:駐車場にしてもアパートにしても、収益が安定するまでに数年かかることが多い。
- 将来の売却時に不利になることも:土地をコンクリートで固めてしまうと、住宅地として売却する際に「撤去・原状回復費用」が発生することがあります。
- 家族・相続人の同意が必要:資産活用は独断で決めず、家族の了承を取ることがトラブル回避の基本。
- 近隣との関係性:利用方法によっては騒音・臭気・景観などで苦情が出る可能性もあります。
まとめ:活用は「立地に合った方法」を選ぶのが成功のカギ
空地を活用する流れは下記のような4ステップです。
- 土地の特性を確認する
- 活用法を選択する
- 初期投資と利回りをシミュレーションする
- 家族や不動産会社と相談し、スタート
我孫子市は駅近〜郊外まで幅広い立地があり、それぞれに適した活用方法が存在します。重要なのは「その土地に合った方法」を選ぶこと。焦らず複数の活用法を比較検討し、専門家の意見も取り入れて最適な道を選びましょう。
第5章 我孫子市の空地事例と成功のポイント

実際に「我孫子市で空地をどう活用したのか」「売却はどのように進められたのか」を知ることは、空地を所有している方にとって大きな参考になります。ここでは、実際にあった事例や想定ケースを交えながら、成功のポイントを整理します。
5-1. 駅近空地を駐車場にして成功したケース
我孫子駅から徒歩7分の場所に空地を持っていたお客様ですが、住宅地の一角という立地を活かして「月極駐車場」として整備されました。
- 2台目・3台目の駐車場を探す近隣住民のニーズとマッチし、稼働率は常に9割以上。
- 初期投資は整地と簡易フェンス設置で100万円程度に抑え、3年目には黒字化。
【POINT】駅近エリアは住宅需要も高いが、将来的に売却する可能性も考えて「砂利敷き+簡易フェンス」で整備したため、原状回復が容易。「とりあえず持ち続けながら収益を得る」という戦略が功を奏した例です。
5-2. 相続で得た郊外の土地を市民農園に転用
天王台駅からバスで15分ほどの郊外地。相続した空地を「市民農園」として貸し出した事例があります。
- 1区画10㎡を年間3万円で貸し出し、20区画を募集したところすぐに満員に。
- 利用者は近隣のシニア層が中心で、地域の交流拠点にもなりました。
【POINT】収益性は高くないものの、固定資産税分をまかなう程度の収入は確保。「地域への貢献」と「最低限の収益確保」の両立に成功した例。
5-3. 空家を解体し、更地を売却して資金化
我孫子市内で空家を相続した方が、維持管理の負担を避けるために建物を解体して売却した事例です。
- 解体費用は約200万円かかったものの、更地にすることで買い手がつきやすくなり、3,000万円以上で売却成立。
- 売却資金を老後資金と子供の教育費に充てることができた。
【POINT】「建物付きの古家」として売るより、更地にしたほうが買い手にとって活用の幅が広がり、結果的に高く売れる場合がある。固定資産税が増える前に動いたことも成功要因のひとつ。
5-4. 工業系企業に資材置き場として貸し出し
郊外の広い土地を、建築会社に資材置き場として貸し出した事例です。
- 月額30万円の賃料で長期契約が成立。
- 定期的な草刈りや整備を企業側が負担する契約とし、所有者の手間は最小限。
【POINT】住宅や農業には適さない立地でも「企業利用」という出口を見つけられる。利用者が法人であるため、安定した契約が期待できる。
5-5. 成功のための共通ポイント
これらの事例からわかるのは、空地活用・売却の成功には共通するポイントがあるということです。
- 立地を最大限に活かす
駅近か郊外か、住宅街か農地か。立地特性を見極めて「合う活用法」を選ぶことが肝心です。 - 初期投資を抑える工夫をする
砂利敷き駐車場や簡易設備など、最初から大きな投資をせずに始めるとリスクを軽減できます。 - 将来の売却を見据える
「いずれ売るかもしれない」と考えて整備をしすぎない。撤去や原状回復コストを考慮することが大切です。 - 専門家に相談する
不動産会社や行政の担当窓口に相談することで、思いがけない活用法や補助制度を知ることができます。
第6章 まとめと今後のステップ
相続やライフスタイルの変化によって「空地を持つことになった」という方は、我孫子市にも少なくありません。この記事では、空地をめぐる課題と解決の選択肢を整理してきました。最後に、重要なポイントを振り返りつつ、今後のステップについてまとめます。
6-1. 空地をそのままにするリスク
「とりあえず持ち続けておこう」と考える方もいますが、空地を放置すると以下のようなリスクが避けられません。
- 固定資産税の支払い
利用していない土地でも税金は発生し、住宅がない更地は軽減措置も効かないため、負担が大きくなります。 - 維持管理の手間と費用
草刈りや清掃、不法投棄防止などの管理を怠れば、近隣からの苦情や景観悪化を招く可能性があります。 - 価値の下落
空地を長期間放置することで、土地の印象が悪くなり、売却時の価格が下がってしまうこともあります。
つまり「何もしない」という選択は、思った以上にコストやトラブルを生み出すリスクをはらんでいるのです。
6-2. 空地を売却するメリット
空地を売却することで得られる最大の利点は 現金化と解放感 です。
売却によって得た資金は相続税や教育費、老後資金などに充てられ、人生設計に大きな安心を与えます。
また、我孫子市は常磐線沿線や成田線沿線という交通の便がよく、首都圏内でも需要が安定している地域です。特に駅近エリアの土地は人気があり、比較的スムーズに売却できる傾向があります。
6-3. 空地を活用するメリットと注意点
「資産として残しておきたい」と考える場合は、土地を活用して収益化する方法があります。
- 駐車場経営
- アパートや賃貸住宅の建築
- 市民農園や貸地
- 資材置き場、太陽光発電用地
いずれも立地に応じた使い方を選ぶことが大切です。ただし、初期投資が必要で、収益が出るまでに時間がかかる点、近隣トラブルや将来的な売却コストが増える可能性がある点など、注意すべき点も少なくありません。
「やりすぎない整備」や「家族・相続人との合意形成」「将来の売却を見据えた柔軟性」が成功の鍵になります。
6-4. 成功事例に学ぶ
この記事で紹介した事例からもわかるように、空地活用や売却には成功のパターンがあります。
- 駅近は駐車場や住宅需要が強い
- 郊外は農園や資材置き場など、立地特性を活かした利用が有効
- 解体して更地にすると売却がスムーズになるケースもある
つまり「立地と目的に応じた最適な選択」をすることが重要です。
6-5. 今後のステップ
もし今、我孫子市内に空地をお持ちで「どうしたらいいかわからない」と感じているなら、次のステップを検討してください。
- 現状を整理する
場所、広さ、固定資産税の額、維持管理にかかるコストを把握する。 - 家族や相続人と話し合う
空地を売却するのか、活用するのか、将来的にどうしたいのかを共有する。 - 不動産会社に相談する
我孫子市に根ざした不動産会社であれば、地域の需要や最新相場に基づいたアドバイスが受けられます。 - シミュレーションを行う
売却した場合の金額、活用した場合の収益性、維持した場合のコストを比較検討。
6-6. まとめ
我孫子市は「都心へのアクセスが良く自然も豊かな街」という特徴を持ち、不動産需要が安定しています。
空地を「売る」「活用する」「持ち続ける」いずれの選択も可能ですが、もっとも大切なのは 自分のライフプランに合った方法を選ぶこと です。
晃南土地では、これまで数多くの空地・空家相談に対応してきました。地域密着の経験とネットワークを活かし、最適な選択肢をご提案します。
「空地をどうするか」迷ったときこそ、ぜひ一度私たちにご相談ください。
我孫子市で空地を成功に導くヒント
我孫子市は「都心へのアクセスの良さ」と「自然の豊かさ」を兼ね備えた地域です。
駅近では住宅・駐車場需要、郊外では農園や資材置き場需要があるなど、立地ごとに異なる可能性を持っています。
「どの活用法が合っているのか」迷ったときは、まずは不動産会社に相談し、シミュレーションを行ってみましょう。晃南土地では地域に根差した事例を数多く蓄積していますので、適切なアドバイスをご提供できます。
晃南土地にできるサポート
晃南土地では、我孫子市に特化した地域密着の不動産会社として、空地の売却・活用・管理まで幅広くご相談を承っています。相場情報のご提供から具体的な活用プランの提案まで、経験豊富なスタッフが伴走します。 空地のことでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

晃南土地について
我孫子・柏エリアに特化した地域密着型不動産会社、晃南土地。我孫子駅前にある弊社は、きめ細やかなサービスで多くのお客様に永く信頼いただいております。賃貸はもちろん、土地の購入や売却、資産運用に関することから、法的手続きや税務のアドバイスまで、お気軽にご相談ください。
不動産の専門知識を持つスタッフが、一人ひとりのご要望やライフプランに合わせた最適な提案を行うなど、安心して取引を進めていただける環境を整えています。
土地の購入や売却でお悩みの方、初めての不動産取引で不安な方も、ぜひお気軽に晃南土地までお問い合わせください。ご相談・ご予約は下記の連絡先までお待ちしております。
【お問い合わせ・ご予約はこちら】
公式サイト:https://kounantoti.co.jp/
電話番号:04-7182-6662
お問い合わせフォーム:https://kounantoti.co.jp/contact/inquiry/
我孫子/柏/流山/印西+東京エリアの空地売却・空地の活用をお考えの方へ
あなたの不動産、晃南土地が買い取ります!